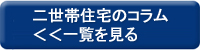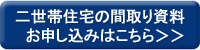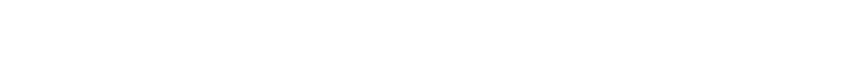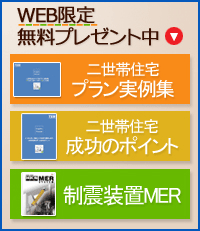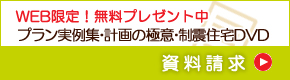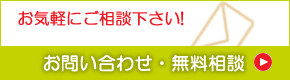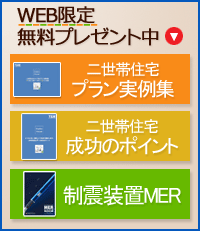玄関は使用時間が短いので 共用にしてもよいのでは
最初から玄関を共用にしたいということは少ない

ほとんどの人が親世帯と子世帯が完全分離のプランを望まれます。
しかし、敷地が足りないことが多々あります。
そうなると共用スペースを作る必要が出てきます。
このような場合、まずは、配置に場所もかかり、設備費用のかさむ水廻りを共用できないかということから考え始めます。
しかし、生活時間の違いや、水廻りに対する思い入れなどから難しい場合もあります。
次に共有できないか検討するのは玄関です。
その理由は、暮らしのなかでいちばん使用(滞在)する時問が短いので、玄関を共用しても両世帯の日常生活にはさほど影響を及ぼさないからです。
表札やポスト、インターフォンをそれぞれ設置すれば、多くの人が玄関の共用に不便を感じることはないでしょう。
物を出し入れする場所は広ければ広いほどよい

最近の住宅では、玄関に収納を配置したり、クローゼットを併設したりするのが当たり前になってきています。この設備にプラスして、二世帯分の靴を収納すると考えるとどうでしょう。
通常の1世帯分の玄関では、狭くて使い勝手が悪くなってしまうのです。
また玄関は、住まいのなかで動線の起点でもあり、要でもあります。玄関を1つ減らすと考えるのではなく、1つ残った玄関をむしろ積極的に利用すると考えて、広めにつくっておくのがよいでしょう。玄関という土間空間は、工夫次第でもっと魅力的な空間になる可能性を秘めているのです。
共用玄関をつかって、各世帯のちょうどよい距離をとる

それは、互いの干渉を最小限にしながら、家族同士の気配をさりげなく感じ取ることができる空間にするためです。
自然の光と風が通るスペースにしたり、夏場の換気塔になるような吹抜けを設けてみるのも、手法の一つです。
こうした設計により、玄関の共用を、1つ屋根の下に暮らしているという安息を得ることのできる空間づくりに昇華させたいものです。
Point 「玄関のほかは分離」の設計手法
●ニ世帯が共用する玄関は広めにする
●大型の玄関収納スペースを確保する
●採光・通風計画を練る
●玄関を気配を感じられる空間としてとらえる
●玄関をニ世帯交流の場とする
●ニ世帯が共用する玄関は広めにする
●大型の玄関収納スペースを確保する
●採光・通風計画を練る
●玄関を気配を感じられる空間としてとらえる
●玄関をニ世帯交流の場とする